「どうぞ!」。意気消沈して帰りかけた私に、人懐っこそうな中年の警察官コンビがパトカーに乗るよう手招きする。2019(平成31)年10月14日、中華人民共和国遼寧省錦州市の警察派出所でのことである。「あなたの出生地を一緒に探してあげましょう!」

私は1944(昭和19)年11月20日、当時は満州と言われた彼地にあった満鉄(旧南満州鉄道)関係の社宅で生まれた。といっても1歳半の乳飲み子で両親と5歳上の姉とともに日本に引き揚げてきてしまった。記憶など全くない。それだけに、「一度はこの目で見て、この足で立ってみたい」と生まれ故郷に強いノスタルジアを感じてきた。しかし、日々に追われ、人生も晩年となり、半ばあきらめかけていた。そんな折、思わぬ公用で韓国行きの機会に恵まれ、隣国でも近い錦州なら足を延ばせる千載一遇のチャンスと出生地再訪を決断した。とはいえ、亡き両親からは多くを聞いてはいない。確たる情報はその両親が申告した戸籍謄本の住所 <満州国錦州市高陽区大正街六ノ壱参ノ壱> だけだった。
数時間も徒労したろうか。とある名刹で足を棒にして青菜に塩となりはてていたら、「どうされましたか?」と天からの慈雨のような日本語で声をかけられた。大連の大学で日本語を学ぶ女子大生だという。地獄で仏だ。子細を話すと、ご親切にも市内観光のために乗ってきた姉夫婦の車で、思い当たる場所を何カ所か回ってくれた。しかし、やはり皆目、見当もつかない。ふと思いついて、「古い記録が遺る役所みたいなところはないものか?」とお尋ねしてみると、それに該当する地区の共産党事務所に案内してくれた。ところが、期待に反して全く要領を得ない。むしろ、迷惑とばかりの冷たい対応だった。女子大生の彼女もさすがに思案投げ首のテイだ。これ以上は迷惑をかけられない。後日お礼をと記念写真を撮って送るという口実で住所を教えてもらい、再会を念じ合いながらお別れした。

とはいえ、なすすべがあるわけもない。天を仰いで、無い知恵に縋ると、ふと浮かんできたのが警察署の存在だった。そして、正直、怖々ながら駆け込んだのが派出所だった。遠来の珍客だったことが幸いしたのだろうか、それなりに熱心に応対してくれた。しかし、70年余のタイムラグに「やはり調べようもない」と窮してしまう。もはや万策尽きたか・・・。悄々として半ば辞去しかけたところに声がけしてくれたのが、冒頭の警察官コンビだったのである。


また走り回る。1時間余も経ったころだろうか。無線にそれとおぼしき場所が分かったという緊急連絡が入ってきた。そこは、錦州駅からほど近く、かつては知る人ぞ知る満鉄の社宅だったという。古くから住んでいる老婦人に付近をパトロール中の警察官に聞き込んでくれたらしい。二人は「ヨッシャ!」とばかり、パトカーのルーフの点滅灯を点け、ボンネット上のサイレンまで鳴らし、現地へ直行した。そこは <中華人民共和国遼寧省凌河区湖北区北路三段申段> と住所表記され、今は政府系の団体事務所で高い塀で囲まれていた。勢い盛んだった二人も「しかるべく許可をとらないと入れない」とすまなそうに肩をすぼめた。そこには満鉄住宅の異名だった〝給水塔〟と通称されていた通り、塀の向こうに、半ば朽ちかけたモニュメントのような古い塔が確かに垣間見えていた。ジッと見詰めていると、なぜか両親の顔も浮かんできた。幼女の姉や、赤ん坊の自分まで、まさしく走馬灯の中に絡み込んでいくようなシーンが巡り巡った。そして、何か確信のようなものも湧き上がる。「オレの生まれ故郷はここだ!」。また、泣けてきた。いつしか誰はばかることなく、号泣していた。時のたつのを忘れて・・・。警官コンビはまた離れて見守ってくれていた。

気がつけば薄暮。立ち去りがたかった。だが、われに返ってみれば、公務中のお二人にこれ以上のご面倒はかけられない。駅まで送ってもらう。そして、何とか形でお返ししたいと持ち合わせ目いっぱいの謝礼を渡そうとした。でも、彼らは笑いながら頑として受け取らない。公務だからなのか、お人柄なのか。ただただ、笑って拒む。そして、逆に「残念だったね」「また来なさい」などと、私をしきりに労ってくれた。私の目頭はまた熱くなった。私はただただ三拝九拝。後ろ髪惹かれながらお別れした。
帰国後、女子大生や警官コンビに御礼を送ったが、期待の返信はなく、その後の縁はつながらなかった。折しも武漢で新型コロナウィルスが発生したとのニュースが流れた。そして、彼の地はこれまで以上に閉鎖的だと評され、さらに近くて遠くなってしまった。
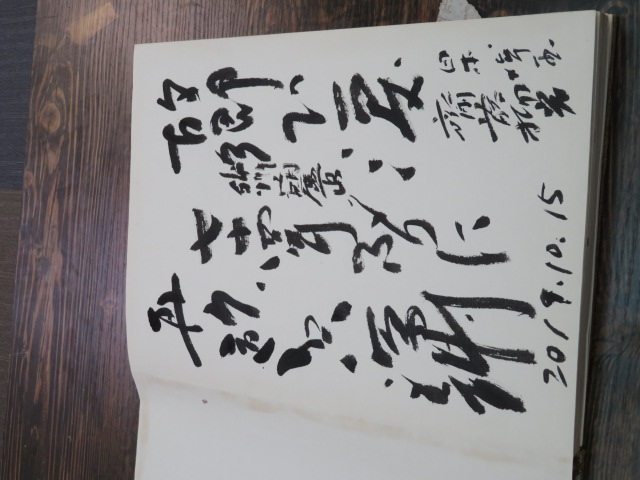

(了)